ChatGPTは便利なAIですが、時には事実と異なる情報を返すことがあります。本記事では、ChatGPTが嘘をついてしまう理由とそのメカニズムを解説し、正しい情報を引き出すためのプロンプト設計術や具体的な工夫例を紹介します。実用的な対策とツールを知り、信頼性の高い会話を実現しましょう。
ChatGPTが嘘をつく理由とは?
ChatGPTは「事実を知らない」から嘘をつく
ChatGPTがあたかも人間のように自然に受け答えするので、「真実を知っている人工知能」だと思われがちですが、実は少し違います。
ChatGPTはインターネット上にある大量のテキストを学習して、「それっぽく見える文章」を生成する仕組みです。
つまり、ChatGPTは事実を「理解」しているわけではなく、**言葉と言葉の並びの確率から、最も自然な回答を予測している**だけなんです。
たとえば、「ナポレオンは何年に生まれた?」と聞くと、それっぽい数字を返してくれますが、逆に学習データにエラーがあったり、曖昧だったりすると、かなり堂々と間違った答えを返すことも。

私も最初「ChatGPTに全部任せれば仕事が効率化できる!」と思ってたんですけど、海外のニュースの引用を頼んだら、記事そのものが存在していないってことがありました…。見た目は本当にそれっぽいのに、調べたら全然見つからなくてビックリしました。
つまり、私たちが思っているよりずっと「賢くはない」んですね。
- ChatGPTは言語のパターンを学習するだけで、事実を理解していない
- 自信たっぷりに嘘をつくことがあるのが逆にやっかい
- 学習データに偏りがあると、誤情報もそれに従って生成されてしまう
嘘を「ついてしまう」構造的な理由がある
もう少し踏み込んで言うと、ChatGPTが嘘をつくのは「嘘をつこうとしてる」わけではありません。
構造的に、**もっともらしい情報を優先的に出力するよう設計されている**から、たとえば「知らないことは知らない」と答えるより、それっぽい答えを出す方を選ぶんですね。
この「確からしく見える」ことが実際には「事実とは違う」ことも多いのが落とし穴です。

あるとき旅行のガイド記事を作ろうと思って、ChatGPTに「京都で穴場のカフェを教えて」って聞いたら、その中の1軒が存在しないお店だったんです。地図や公式サイトも見つからず、結局全部自分で調べ直しました…。
こういったエピソードからも分かるように、ChatGPTにはいくつかの注意点が存在します。
- ChatGPTは事実より「自然な言い回し」を優先する
- 「知らない」と言う訓練が不十分な場合がある
- 架空の情報(ホールハルシネーション)を含むこともある
嘘を防ぐために知るべき仕組み
ChatGPTがどうやって答えを作っているのか?
まず、「ChatGPTって、なんでそんなに自然に会話できるの?」とよく聞かれます。実はこれ、膨大なインターネット上のテキストを使って訓練されたAIだからなんです。
ただしポイントは、ChatGPTが「人間のように考えてから答えているわけではない」ってこと。過去の情報や文章パターンを元に、次に来そうな単語を推測して答えているだけなんです。
つまり、ChatGPTは本当かどうかではなく、「それっぽく見える答え」を返すように設計されているんですね。
これを理解していないと、「ChatGPTが言ってるんだから正しいはず」と思ってしまいがち。でも事実としては、**AIが自信満々に嘘をつくこともある**ってこと、知っておいたほうがいいです。
私自身も、「ChatGPTが教えてくれたんだけど、全然違うじゃん!」という経験が何度もあります(笑)。だからこそ、まずこの“仕組み”を理解するのが第一歩なんですよね。
- ChatGPTはインターネット上の情報を参照して学んだAIであって、「情報の真偽」を判断していない
- もっとも自然と思われる次の単語を選ぶ方式(=確率的予測)で会話を構成している
- 問われた内容について自信ありげに返すけど、それが嘘の場合もある

前にレアな映画の情報を聞いたら、もっともらしいストーリーとキャストまで教えてくれたんだけど、実在しない映画だったの!あれはちょっとショックだったな〜。
なぜ嘘っぽくなるのか?構造的な問題を理解しよう
さっき話したように、ChatGPTは「正しいことを言おう」としているわけじゃないんです。キーワードの並びや使われ方を学習して、言語の型を予測して返しているだけ。
そのため、**事実確認をする知識ベースや検索エンジンとの連携がないと、過去学んだ記憶だけで答えてしまう**んですよね。
これは人間で言えば、「うろ覚えのことをドヤ顔で話す人」みたいなもの(笑)。正しく思ってるけど、実は勘違い、みたいな。
また、トレーニングに使われた情報元が古かったり、一部誤情報が混じっていた場合、それも出力に影響します。
だから、ChatGPTを使うときは「人の意見を聞いているつもり」で使う感覚が近いかも。最終判断は、自分でチェックしないといけません。
- ChatGPTは情報の「もっともらしさ」を優先して返答している
- 事実確認のプロセスやリアルタイム検索の仕組みは基本的にない(※有料版でのWebブラウジング機能は例外)
- 答えが誤っている可能性を前提に、確認する目を持つべき

「この健康情報、本当かな?」と思って調べたら、出典が曖昧で…。焦って自分でも検索したら、全然違うことが書いてあったんだよね。それからは、必ず自分でも確かめるようにしてるよ。
ChatGPTに嘘をつかせないプロンプト設計術
「正しい質問」をしないと、正しく答えてくれない
ChatGPTは、人間のような会話ができるAIですが、「事実」と「ただのそれっぽい回答」を区別して出しているわけではありません。そのため、プロンプト(指示する文章)の書き方次第で、かなり曖昧な情報や、場合によっては**誤った内容(=嘘)**を返してしまうことがあります。
たとえば、あいまいな質問「最近話題の健康法って何?」みたいな聞き方をすると、ChatGPTはネット上の噂や古い情報まで混ぜてくることがあります。つまり、正確な情報を引き出したいなら、それにふさわしい質問の仕方=プロンプト設計が必要なんです。

以前、「歴史上の人物で最も偉大な科学者は?」と聞いたら、ChatGPTがなぜか架空の人物を作り出して出してきたんです(笑)。そのときは曖昧さが招いた結果だと気づきました。
要するに、ただ質問するだけじゃなく、「どう答えてほしいか」まで考えて入力する必要があるんですね。
- あいまいな言い回しは避け、具体的な条件を入れる
- 「事実ベースで答えて」と明示するプロンプトを使う
- 返された答えの出典など引用元も要求する
信頼性を担保する指示ワードを使おう
もう一歩踏み込むと、ChatGPTに「どう答えてほしいか」を明確に伝えるための“型”を使うと効果的です。たとえば、「事実に基づいて、証拠がある情報のみを挙げてください」「URLや論文など引用元を明記してください」などのフレーズを入れておくと、より正確で裏付けのある情報が出やすくなります。
ぼくが最近よく使っているのが、「2023年以降の信頼できる情報に基づいて、ステップごとに教えてください」っていうテンプレ。これを使うだけで、情報の精度がグッと上がりました。

体感ですが、プロンプトに「最新の論文ベースで」とか「信頼性を示してください」と書くだけで、**想像ベースの回答が激減**するんですよ。試してみる価値アリです!
- 「○○年以降の情報で」と指定する
- 「出典付きで回答してください」と指示する
- 「事実ベースで、感想や憶測を含めずに」と念押しする
プロンプトの工夫次第で、ChatGPTの精度は本当に変わります。逆に言えば、こちらがうまく聞いてあげないと、いくら高度なAIでも信頼できる回答は得られないんです。
信憑性を高めるプロンプトの工夫例
「曖昧な質問」より「具体的な条件」を
ChatGPTに質問をする時、聞き方次第で回答の正確性って大きく変わるんです。
たとえば「戦国時代の有名人を教えて」とだけ聞いた場合、人によって「有名」の定義が違いますし、ChatGPTも抽象的な判断を迫られることに。
でも、「戦国時代の武将で、織田信長と直接関係のあった10人を、名前・関係性・年分と一緒にリストアップして」と聞けば、情報の整合性がグッと上がります。

私も昔、「おすすめの健康食を教えて」とだけ聞いた時、根拠も曖昧な食品ばかり返ってきて正直ガッカリ…。でも、「医学的根拠があるものに限定して、かつ2020年以降の研究を踏まえて」と条件を足したら、出てくる情報の質がぜんぜん違って驚きました。
- 質問の意図や対象、条件を明確に記述する
- 必要あれば「対象の年代」「参照元」なども指定する
- 抽象的な言葉(例:すごい、有名など)は避ける
ソース明記を求めるプロンプトで精度アップ
ChatGPTはソース(出典)があいまいなことも多いんですが、**「出典を明記してください」**と書くだけで、格段に回答に責任感が出てきます。
「この記事の内容をもとに要約し、さらに参考にしたページURLも示して」と要求すれば、出典付きで答えてくれる確率が高まります。

仕事で調査資料を作っていた時に、「学術的な情報のみ・出典リンク付きで」と条件をつけて聞いたら、ちゃんとGoogle ScholarやPubMedにあるようなリンクを教えてくれて助かりました。**リンクがあると信頼性が一気に上がりますよね。**
- 「出典・参考リンクを必ず明示して」と明記する
- 「信頼できる情報源のみに限定して」と条件づける
- 特定の媒体・組織(例:WHO、統計局など)を指定するのも有効
ChatGPTに正確な答えをもらうには、こちらの聞き方がカギを握っています。
あいまいなまま丸投げするのではなく、具体性・制約・出典要求の3つを意識してプロンプトを組み立てると、信憑性はぐっと高まりますよ。
検証とファクトチェックの重要性
AIが出す情報が100%正しいとは限らない
ChatGPTは膨大な情報をもとに言葉を生成していますが、インターネット上にある情報がすべて正しいわけではないため、出力される内容にも事実とは異なることが含まれる可能性があります。
たとえば、ネット上でよくある「◯◯は健康にいい」という情報が、実は一部の人にとっては有害だったり、数年前の誤った研究を元にしていたりすることがあります。
AIは「もっともらしく」見える文章を作るのが得意なので、初めて見る内容でもつい信じてしまいがち。でも、それが嘘や誤情報だったら……大問題ですよね。

以前、ChatGPTに「ある健康食品が花粉症に効くか」を聞いたんだけど、かなり事実っぽい説明で「効果がある」と書かれてたの。気になって調べたら、実際には信頼できる研究はなかったっていう…。騙されそうになったよ〜。
- AIの出力はあくまで「確率的な文章生成」にすぎない
- 正しそうに見えても、情報源が不確かであることが多い
- 事実確認しないまま使用すると、誤解・誤情報の拡散に繋がる
自分で検証するクセをつけることが信頼性を高める
ChatGPTなどの生成AIを使うときに大事なのは、出てきた答えをそのまま信じないこと。経歴のあるサイトや専門家の意見、統計データなどと照らし合わせて「本当に合っているか?」を確かめるクセをつけるのがカギです。
特に医療や法律、歴史といった分野では細かなニュアンスが結果に大きく影響するので、Wikipediaや政府機関の公式サイトを利用して裏取りするのがおすすめです。

最近、本の要約をChatGPTにお願いしたんだけど、章立てが明らかに違ったのね。それでAmazonの商品ページや著者のサイトで確認して、やっぱり間違ってたと判明。結局、自分でちゃんと調べないと駄目だな〜って実感したよ。
- AIの出力後は「必ず」公式ソースと照らし合わせる
- 重要な情報は3つ以上の異なる信頼ソースで確認する
- 怪しいと思ったら深掘り調査。習慣づければ自然と見抜ける
おすすめの外部ツールと活用法
事実確認には「信頼できるツール」を使おう
ChatGPTを使っていると、「本当かな?」と思う情報に出くわすこと、結構ありますよね。
実際、AIは完璧ではないので、誤情報を出すこともあります。だからこそ、**外部の事実確認ツールを活用して、精度の高い情報収集を心がけることが大切です。
以下で、情報の信頼性を確認したいときに便利なツールとその使い方を紹介します。
- Google Scholar(グーグル・スカラー):信頼できる論文や学術ソースを検索可能
- Wikipedia(ウィキペディア):関連知識の概要を把握できるが、出典チェックは必須
- FactCheck.org / Snopes.com(英語):政治や社会の誤情報に対するファクトチェックを提供
- 日本ファクトチェックセンター:日本語のニュースやSNSの誤解を検証
- Google検索+「site:.go.jp」「site:.edu」:公的機関や教育機関の情報を狙って検索
私が実際に助けられたツールの使い方
正直、ChatGPTが「一見もっともらしいけど間違った答え」を返してきたこと、何度もあります。
たとえば以前、歴史系の内容について質問したときに、ChatGPTが「〇〇年に××戦争が起きた」と答えてきて。一瞬信じかけたんですが、念のためにGoogle ScholarとWikipediaで確認したら、全然違う年だったんですよね。
それ以来、**ChatGPTの回答を鵜呑みにせず、外部ソースでの検証がマスト**って思うようになりました。

私はよくGoogle Scholarを使って、ChatGPTの答えと照らし合わせて見てます。専門的な内容には特におすすめ!
要点をまとめると…
情報の正確性を確保するには、ChatGPTの出力内容を検証・補完するためのツールが欠かせません。
- 学術的な内容ならGoogle Scholarが最強
- Wikipediaも使えるが、出典元をチェックするクセをつけよう
- ニュース系はファクトチェック専門サイトがおすすめ
- 日常使いや日本語では「日本ファクトチェックセンター」が便利
- 検索時は「.go.jp」「.edu」などの信頼ドメイン指定が有効
分野別に見る正確性の傾向と対策
分野によって「精度のバラつき」があるって知ってた?
ChatGPTがすべての分野に均等に強いわけじゃないんですよね。分野によって得意・不得意がけっこうハッキリしています。
たとえば、英語文法やプログラミングの基本文法なんかは割と得意。でも医療や法律の話になると、ちょっと怪しい回答が出ることもしばしば…。
私自身も以前、「法律相談」のプロンプトでChatGPTを使っていたところ、まるで専門家っぽい口調で話してるけど、実は法的に間違った説明をされていたことがありました。あとで弁護士の知人に聞いてやっと気づいたんですけど、ちょっとゾッとしましたね。
だからこそ、「分野によって回答の正確性が異なる」ってことを前提に、プロンプトを工夫したり、回答に対して構え方を変えたりする必要があるんです。
この“精度の違い”を踏まえて、分野別の特色と注意点をまとめてみました。
- 英語・外国語学習:比較的正確だが、口語表現に要注意
例文のニュアンスが自然かどうかは、実際のネイティブ表現と少しずれることも。音声読み上げやネイティブ監修の教材と併用しよう。 - 法律・医療系:専門性が高く、嘘のように正しく聞こえる誤情報も多い
AIの守備範囲外の領域なため、最終的には専門家に確認を。プロンプトでは「これは一般論ですか?それとも法律に基づいてますか?」と聞くのもアリ。 - テクノロジー・プログラミング:コードの基礎生成には強いが、最新フレームワークなどは情報が古い場合も。GitHubや公式ドキュメントも交えて検証を。
- 歴史・文化:元ネタが書籍や記事ベースなので、ウワサや都市伝説まで拾いやすい。複数の出典を確認しながら使おう。
- ビジネス戦略・マーケティング:概念的な説明はうまいけど、市場環境や数値データは時代遅れになっていることもあるので、最新の事例と照らし合わせると◎。

私も一度、マーケティングのトレンドをChatGPTに聞いたら、2019年ごろの古い戦略を堂々と勧められまして…。一見、整ってるようで「今」にはそぐわないアイディアだったんですよね。やっぱり、現在の情報と付き合わせるって超大事だなと思いました。
要するに、ChatGPTは「何でも知ってる万能ツール」じゃなくて、使うテーマごとに信頼度が変わる道具なんです。
だから、プロンプト作成するときには”どの分野か”を意識して、過信しないことが必要ですね。
まとめ:信頼できる情報を得るために
ChatGPTの出力を信じすぎないことが最大の防御策
いろいろな調査や体験談を通してわかったことがあります。それは、ChatGPTだけに頼って情報を判断しないことが、間違った情報を防ぐ一番の近道だということ。
ChatGPTは非常に便利で賢いツールですが、**絶対に正しい情報を出すわけではない**、ということをまず念頭に置いておくべきです。
たとえば、私自身、以前「ChatGPTに旅行プランを立ててもらう」ってことを試したことがあるんです。それ自体は面白い試みだったんですが、実際に提示された観光地のひとつがもう何年も前に閉鎖されていたんですよね…。そのときに、「あ、これはちゃんと調べ直さないといけないな」と思い知らされました。

ChatGPTを使うのは楽しいし便利!でも「提案のきっかけ」として使って、自分でもちゃんと検証する、ってバランスが大事ですね。
- ChatGPTは完璧な知識ベースではない
- 情報を”信じる”のではなく、あくまで”参考”にする
- 自分の目的に合わせてプロンプトを工夫することで精度が上がる
信頼性を高めるためにできる3つのこと
これまでお伝えしてきたように、ChatGPTに嘘をつかせないためには使い方の「工夫」が必要になります。以下のポイントは、今すぐ試せる基本中の基本です。
たとえば私が情報を精査するときは、ChatGPTの回答を**必ず2つ以上の信頼できる外部ソース**と突き合わせるようにしています。Google Scholarや公的機関のサイトなどですね。専門性の高い分野ほど、このステップは欠かせません。
また、プロンプトの文末に「出典も明記して」と入れるだけでも、信頼性の高い情報を引き出せる確率がグッと上がります。

ChatGPTって、こちらのプロンプト次第で大きく答えが変わるから、質問の仕方って本当に大事ですよね。ちょっと面倒だけど、コツを掴むと一気に便利になります!
- 質問の仕方(プロンプト)を具体的にする
- 出典や参照先を求める一文を加える
- AIの回答をファクトチェックする習慣を持つ
AIとの付き合い方は「うまく使えば紙以上、本気で使えばプロのツール」って感じかもしれませんね。逆に、使い方を誤ると誤情報の発信源にもなりかねないので、今後ますますリテラシーが求められる時代になっていくと思います。
日常の中で、ChatGPTを単なるおしゃべり相手ではなく、「賢く使う相棒」として使いこなせる人が、これからの情報社会を生き抜いていくカギを握るのかもしれません。

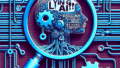
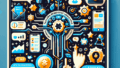
コメント