ChatGPTは便利なAIツールとして注目を集めていますが、「嘘をつく」と言われることもあります。本記事ではChatGPTの仕組みや誤情報の原因、実際の事例をわかりやすく解説し、ユーザーが賢く利用するための対処法と今後の課題を探ります。
ChatGPTは本当に嘘をつくのか?
ChatGPTは意図的に嘘をついているわけではない
最近、「ChatGPTって嘘つくよね?」なんて話を耳にすることが増えました。
でも、これって本当に“嘘”なんでしょうか?
まず押さえておきたいのは、ChatGPTは人間のように感情も意図も持たないAIという点。
つまり、自らの意思で何かを「隠す」「ごまかす」「騙す」なんてことはできないんです。
ChatGPTは、大量のテキストデータを学習して、それっぽい答えを導き出すツールなんですが、時には情報の正確性を欠いてしまうことがあります。
でもそれは「嘘」というより、「間違い」や「勘違い」と言ったほうがしっくりきます。

実際、私もChatGPTに料理レシピを聞いたとき「この材料ほんとに使う?」って思うようなことがあって、調べてみるとやっぱり間違ってた…。でも、間違えてるってわざとじゃなくて、ただ情報が古かったり不正確だったみたい。
- ChatGPTは自分の意志で発言していない
- 嘘ではなく「誤情報」と考えるのが正確
- 人間のように意図的な嘘をつくことはない
誤情報はあるけれど、それを「嘘」と捉えるのは誤解かも
「そもそもAIに“嘘”という概念を当てはめること自体が違うのでは?」という視点も大事です。
嘘とは『事実ではないことを、事実のように言う意図』がある時に成り立ちますよね。
ChatGPTにはその“意図”がないため、たとえ間違った発言をしてしまったとしても、それは“嘘”ではないということです。
もちろん、間違ったことを言われた側からすれば混乱します…。私も以前、歴史の年号を聞いて、「そんなバカな!」というミスも経験しました。
でも、それは単に情報の更新が追いついていなかったり、学習データのバイアスによって誤解が生まれただけなんですよね。

「AIが嘘をつく」と思うとちょっと怖いけど、そうじゃなくて単に情報が完璧じゃないだけなんだな、って思うようにしてます。
- 嘘=意図が前提だが、AIに意図はない
- 出力される誤情報も「間違い」や「不正確」なだけ
- ChatGPTは“嘘つき”ではなく、未熟な情報提供ツールと捉えるべき
ChatGPTの仕組みと回答生成プロセス
ChatGPTはどうやって「言葉」を作っているの?
ChatGPTって、まるで人と話しているみたいに自然な返答をしてくれますよね。でもどうやって、その文章を思いついてるんだろう?って不思議に思いませんか?
実は、ChatGPTは「言葉の次にくる言葉」を予測しているだけなんです。過去の会話や文章データを大量に学習して、「この言葉のあとにはこれが来そう!」と確率的に判断して文章を作ってるんですね。
たとえば、「私はコーヒーが〇〇。」と入力すると、「好きです」「嫌いです」など、文脈に合いそうな言葉を予測して文章を完成させます。つまり、あくまで“もっともらしい文”を作ることに特化してるんです。
これは人間が論理的に考えて答えるのとはちょっと違ってて、ChatGPTは“考えてから話す”わけじゃないんですよね。

初めてこの仕組みを知ったとき、「じゃあ間違ってても、堂々と話すこともあるんだ!」とちょっとびっくりしました。確かに、何回か質問したときに違う答えが返ってきた理由がわかった気がします。
- ChatGPTは単語のつながりを予測する「言語モデル」
- 情報の正確性より「文章として自然かどうか」が重視される
- 事実かどうかを判断する機能は持っていない
正しい答え=正しい仕組みとは限らない
仕組み的に言えば、ChatGPTは“正しそうな言葉の並び”を生成するのが得意です。でも、「正しそう=真実」とは限りませんよね。
実際に私も、「日本で一番高い山は?」と聞いたら「富士山です」って即答されたけど、「富士山は東京にあります」って続けて言われたことがあります(汗)。いや、それは間違ってるでしょ…と突っ込まずにいられませんでした。
これは、Web上に「富士山 東京」というキーワードが混ざった記事が多かった影響かもしれません。つまり、学習データに基づいて、本当っぽいけど違う答えを出してしまうことがあるんです。

「AIが言ってるから正しいはず!」って思って信じちゃったんですけど、冷静になって調べたら間違ってることが判明…。以来、ChatGPTの答えも一度ググって確認するようにしてます。
- ChatGPTは「真偽」より「自然な文章」を優先
- 時には、データのバランスで誤情報を返すことも
- ユーザーの側でも正誤チェックが必要
よくある誤情報とその事例
うっかり出る“それっぽいウソ”に注意
ChatGPTを使っていて、「それっぽく見えるけど実は事実と違う」情報を返された経験、ありませんか?
実際に、ChatGPTはまるで本物の知識のように、実は正しくないことを言ってしまうことがあるんです。
たとえば、私は以前「日本の総理大臣の歴代リスト」を聞いたときに、「存在しない人物」が混じっていたんですよね。

まさか「架空の総理大臣がいる」なんて思わなかったので、一瞬信じて調べちゃいました。後からウィキペディアで見て「え、そんな人いないじゃん!」って驚いたのを覚えています。
まぁ実際、ChatGPTは言語モデルなので、事実チェックというより「過去の言語パターン」から答えを生成してます。だから、時々間違ってることも言っちゃうんですよ。
特に要注意なのは、以下のようなケース。
- 実際には存在しない人名や書籍・論文をそれっぽく生成する
- 誤った日付や出来事を本当のように断定する口調で話す
- 医療や法律など専門知識が必要な分野で誤情報を提示する
こういう誤情報って、見た目がもっともらしいからこそ信じやすくて危険なんですよね。
とくに**専門用語を混ぜてくると「正しそう」に見える**罠、本当に要注意です。
論文を“でっち上げ”!?信じすぎ禁物
ChatGPTがよくやっちゃう代表的なミスの一つが、実在しない論文や本のタイトル・著者名をあたかも本物のように出してくること。
ある大学生の友達が、「卒論で使えそうな参考文献を出して」とChatGPTに聞いたら、知らない本や論文がずらっと出てきたんです。

それ全部メモして図書館に行ったのに、1冊も存在しなかったとか言ってて…。ChatGPTに文句言っても遅いよって苦笑いしてました(笑)
これってつまり、「出典があるように見せかけるけど、実は全部創作(ハルシネーション)」の状態。
**信ぴょう性が一番大事な場面で、まさかの“でっち上げ”**って、正直ショックですよね。
- 存在しない論文や本のタイトルを堂々と紹介してくる
- 実在する論文でも著者名や出版年が間違っていることがある
- 「参考文献」として鵜呑みにすると信用問題にも発展しかねない
だから、ChatGPTの情報を使うときは、最後は必ず自分でも調べて裏付けをとるのが鉄則ですね。
情報の“たたき台”には便利だけど、“最終結論”にしちゃダメ、ってところがポイントです。
なぜChatGPTは誤った情報を出すのか
ChatGPTは「知っている」のではなく「それっぽく話す」
まず、ChatGPTがそもそも「知っている」かどうかというと、実は知識を持ってるわけではないんだよね。
ChatGPTは、いろんな文章データを学習して、あたかも人間のように会話をするように設計されたAIなんだけど、事実を確認して答えてくれているわけじゃない。そう、言ってしまえば「それっぽい回答をつくる達人」なの。
だから、元になってる情報源が間違っていたり、質問の文脈を読み違えたりすると、「嘘」に聞こえるような誤情報を出してしまう。
たとえば、僕が前に「2022年のサッカーW杯優勝国はどこ?」って聞いたら、「ドイツです」って返ってきたの。いやいや、優勝したのはアルゼンチンだから!と思って、ちょっとびっくりした(笑)。
でもこれ、ChatGPTがわざと嘘をついてるわけじゃないんだよね。間違った情報を「もっともらしく」話してしまってるだけ。**つまり、嘘というより勘違いのプロフェッショナル**、って感じ。
- ChatGPTは意味を理解しているわけではない
- 学習したデータが間違っていればそれを繰り返す
- 質問の意図次第でズレた答えが出てしまう

ChatGPTに「歴史上の人物に関する小ネタ」を聞いたら、めちゃくちゃ話が面白くて感動したんだけど、後から自分で調べたら半分くらいはウソだった(笑)。でも、そのおかげでちゃんと調べようと思ったし、ちょっとしたキッカケにはなったかな。
「完璧」を求めると危険。AIは道具であって先生ではない
つまり、ChatGPTの出す誤情報って、悪意があるわけじゃなくて、仕組み上そうなっちゃうんだよね。
だからこそ、僕らがChatGPTを使うときに大事なのは、「正しいことを言う前提」で信じすぎないこと。
たとえば、頼れる友達に相談したら、たまに間違ったアドバイスが返ってくる…みたいなイメージで接するのがちょうどいいんだと思う。
**AIはツール。自分自身のチェックが大事**ってことを、忘れないで使うことがいちばんの対策なんだよね。
- ChatGPTは正しさを保証しているわけではない
- 「わからないときは自分で調べる」姿勢が大切
- 間違いを責めるより、正しく使う力が求められる

最近は、ChatGPTの情報をそのまま使うんじゃなくて、参考にして自分でもちゃんとググるようにしてる。「なるほどな〜、そういう考え方もあるのか!」っていうヒントをもらう感じで使ってるよ。
ChatGPTの誤情報との向き合い方
ChatGPTは時々堂々と間違ったことも言う
まず、知っておいてほしいのが、ChatGPTは「嘘をつこう」として嘘を言っているわけではないんです。
AIとして、あくまで過去に学習した膨大なテキストデータから「もっともらしい答え」を生成しているだけ。だからこそ、ときには事実と違うことでも、あたかも正しいかのように話すんです。
ぼく自身も、旅行先で「ここはウミガメも見られるよ!」って言われた場所に行って、全然そんなスポットじゃなかった時にはビックリしました(笑)。調べたら、どうやら他の観光地の話と混ざっていたようで。
このように、ChatGPTの出す情報は、**一見正しく見えても100%信じないこと**が鉄則です。

「え?こんなに詳しいことまで知ってるの!?」って思わせるのがChatGPTのすごさ。でも、だからこそ間違いにも気づきにくいから注意が必要なんです。
- ChatGPTは間違っていても自信満々に話すことがある
- 意図的な嘘ではなく、文脈や情報の誤解釈による誤り
- 見栄えがいい文章=正しい情報、ではない
間違いを見抜くための3つのチェック方法
じゃあ、どうやって誤情報を見抜けばいいの?って話ですが、便利な方法がいくつかあります。
ぼくがいつもやっているのは、**必ず別のソースでも確認すること**。たとえば、ChatGPTが教えてくれた情報をそのまま鵜呑みにせず、他の信頼あるサイトやGoogle Scholar(文献検索)で裏をとるんです。
あと、便利なのが「引用元ありますか?」って聞くこと。ChatGPTは通常、明確な出典を出さないことが多いんですが、自信がある回答なら関連文献も添えてくれたりします。
それと、数字や統計データはとくに注意。出典がない場合は、真偽を自分で調べ直したほうが安全です。
- 他の信頼できる情報源で裏を取る
- 必ず「出典は?」とAIに聞いてみる癖をつける
- 特に専門分野やデータには慎重になる

以前、ChatGPTにビタミンDの推奨量を聞いたら、国が定めてる数値と全然違って焦ったことがありました。自分で厚労省のページ確認しといて良かった〜!
ChatGPTとの上手な付き合い方
AIであるChatGPTは、あくまで「サポート役」。人間の代わりに完全に正確な知識をくれるわけじゃない、っていうスタンスで付き合うのがベストです。
特に医療や法律、歴史的事実など、専門性が高い内容は間違いが混じりやすい。誤解を避けるためにも、自分でも調べたり、詳しい人に話を聞いたりすることが大事ですよ。
手軽で便利な存在ではあるけど、**必ず「二重チェック」する癖を持つ**こと。これさえ意識しておけば、ChatGPTとの付き合い方が一気に楽になります。
- ChatGPTは「参考意見」として扱うとちょうどいい
- 専門的な話ほど慎重に扱う
- 鵜呑みにせず、自分の判断力を鍛えるツールにする
ChatGPTと倫理:AIに嘘の責任はあるか
AIが嘘をつく? それは「嘘」なのか
まず、ChatGPTが出す誤った情報は、私たち人間が意図的につく「嘘」とは少し性質が違います。
ChatGPTは、「嘘をつこう」として情報を作っているわけではなく、あくまで過去のデータに基づいて「もっともらしい」回答を予測しながら文章を生成しています。
つまり、正確な情報だろうが、間違った情報だろうが、「こう言えば自然だよね」という確率論に基づいて発言しているにすぎないのです。
でも受け取る側からすれば、そこに誤情報があれば、やっぱり「嘘をつかれた」と感じてしまいますよね。
実際に私は以前、「2022年のノーベル文学賞受賞者は?」とChatGPTに尋ねたところ、存在しない人物名を堂々と答えられてビックリしました。

そのときは「え、本当に?」と思って調べ直したら、全然違ったんですよ。なんというか、すっごく信じてしまってたので余計にショックでした。
- ChatGPTは人間のように意図的に嘘をつけるわけではない
- 誤情報は「もっともらしさ」を優先した結果にすぎない
- 人間が信じやすいという点で、結果的に「嘘」と受け取られてしまう
責任は誰にある? 開発者・利用者・社会の三者構造
では、ChatGPTの誤情報に対して誰が責任を負うべきなんでしょうか?
「AIに責任はない」とよく言われます。確かにAI自体は意識も価値観もないので、「ウソをついてはいけない」という倫理観は持ちません。
でも、だからといって「誰の責任でもない」とするのは少し乱暴な話ですよね。
結局のところ、AIを開発した人間や、それを使う私たち一人ひとりが、全体としてその影響力に責任を持たなくちゃいけないと思うんです。
特に広く使われるツールである以上、「誤情報の拡散」が社会的にどれほど影響力があるかは、絶対に無視できません。
私自身、仕事でリサーチにChatGPTを使っていて、そのまま信じた情報をクライアントに報告したことがあったんですけど、あとから事実と違うとわかって本当に焦りました…。

そのとき、自分の注意不足をものすごく反省しました。ツールは便利だけど、それ以上のリテラシーが必要だと痛感しましたね。
- AI自身に責任を問うのは現実的ではない
- 開発者は更新・改善を通じて正確性を高める責任がある
- 利用者はリテラシーを上げ、情報の裏取りをするべき
信頼できるAIとしての今後の課題
精度向上のカギは「学習データ」と「人のフィードバック」
ChatGPTをはじめとしたAIは、大量の文章データを読み込んで「言葉のパターン」を学んでいます。
でも、そのデータの中に誤情報や古い知識があると、それをそのまま覚えてしまうこともあります。
だから最近、AI開発では「人によるフィードバック」や「信頼性の高いデータ」での学習が強化されています。
これは、AIに正しい知識を教える“先生役”の人が増えている感じですね。

前にChatGPTで医療系の質問をしたんだけど、ちょっと古い情報をもとにして答えてきたことがあって…。あとで調べたら最新のガイドラインと違ってたの。そこから、AIの回答をうのみにしすぎないように意識するようになったよ。
- AIの精度向上には「信頼できるデータ元の選定」が不可欠
- 人間によるフィードバック(Reinforcement Learning from Human Feedback)が改善に効果的
- アップデート頻度を高めることも“鮮度の高い知識”を保つために重要
AIも学習する「素材」が大事なんですよね。
料理と一緒で、新鮮で良質な材料(データ)があるほど、美味しい(正確な)答えが出てくるんです。
ユーザーのリテラシーも問われる時代に
AIが進化しても、私たちユーザーの側にも求められてくるものがあります。
それは「少し立ち止まって考える力」、つまり**情報をうのみにせず、自分で検証しようとする姿勢**です。
AIがどんなに賢くなっても、100%正確とは限りません。
これからのAI活用では、「AIの答え+自分の判断」で進めることがベストなんです。

私は最近、自分が読んだ情報をAIにも聞いて「本当に合ってる?」って確認する使い方をしてるよ。そうすると、逆に「あ、意外と間違えてるな」って気づけたりして、昔より情報に対して敏感になった気がする。
- ユーザーが「検証の習慣」を持つことが重要
- 複数の情報源と照らし合わせてAIの回答を確認しよう
- **AIを“共に考えるパートナー”として使う意識**が鍵
まとめると、AIがもっと信頼できる存在になるには「AI側の精度向上」と「私たちの使い方」の両方が大事なんですね。
ちょっと頼れる友達くらいの感覚で接するのが、今のところちょうどいいバランスかもしれません。
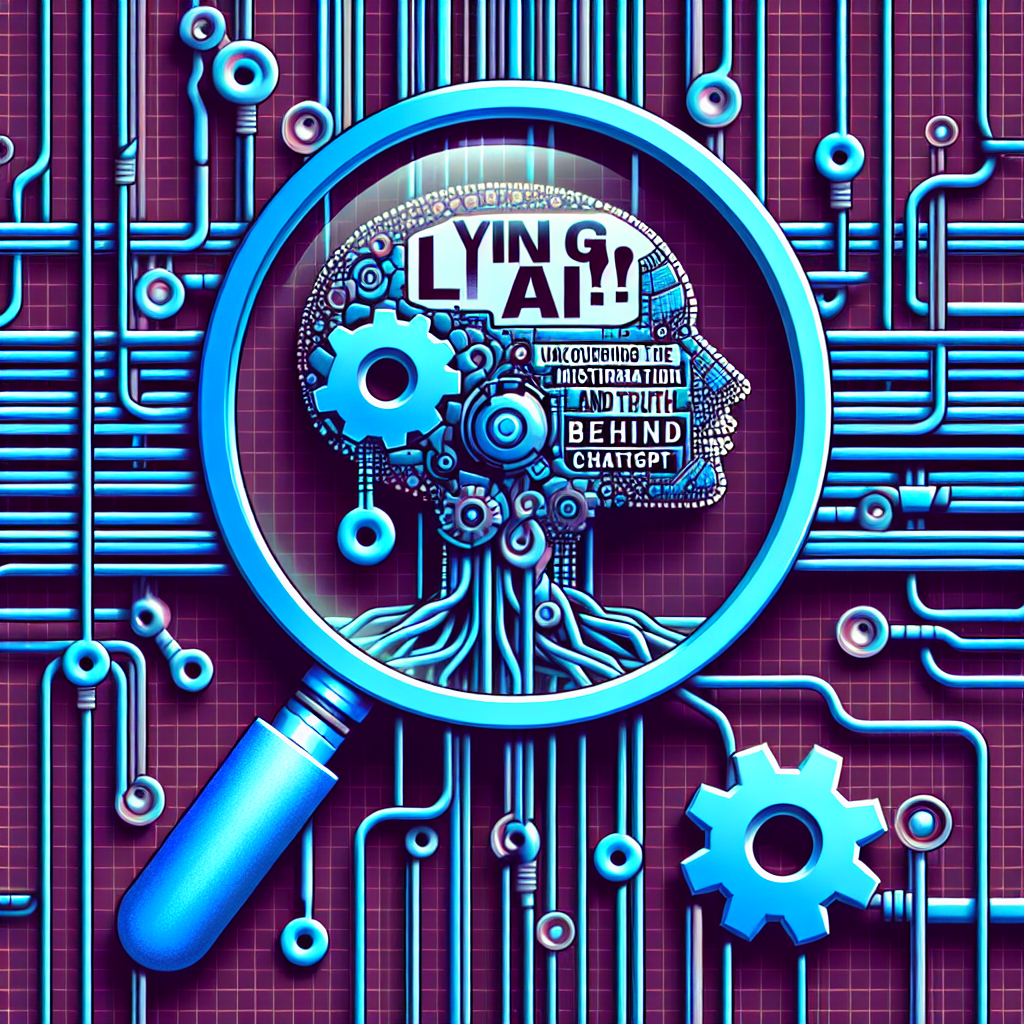
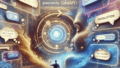

コメント